
「日本をデザインする」をヴィジョンのひとつに掲げる武蔵野美術大学ソーシャルクリエイティブ研究所。2月27日、同研究所主催のイベント「政策のデザインの可能性」が市ヶ谷で開催された。2018年に経済産業省が発表した「デザイン経営」宣言など、近年、公共政策の領域でもデザインの視点が大きな注目を集めている。またその潮流は、政策立案のプロセス自体も変えつつあるという。「政策」と「デザイン」のテーマから、いま、語るべき課題とは何か。経産省デザイン政策室の菊地拓哉さん、特許庁の橋本直樹さんらをゲストに迎えたイベントの模様をレポートする。
政策の立案プロセスをリデザインする
新型コロナウィルス拡散防止のため、一般の参加者を入れず、配信のみで公開された今回のイベント。前半で、4人のスピーカーが話題提供のプレゼンテーションを行った。
特許庁の橋本直樹さんは、経産省でクールジャパン政策などに関わったのち、ニューヨークのパーソンズ美術大学へ留学した異色の経歴の持ち主だ。現地では、分野を超えた社会的なデザイン実践を考える「トランス・ディシプリナリー・デザイン」を研究。末期癌患者と病院のコミュニケーションを助けるツールキットの開発などに関わった。
修士論文では政策のリデザイン、とくに政策立案のプロセスに着目した。政策立案の流れは大きく「立案」「意思決定」「実施」「評価」に分かれる。橋本さんは「立案」をさらに細かく「課題設定」「アイディエーション」「具体化」に分け、改善点を探った。
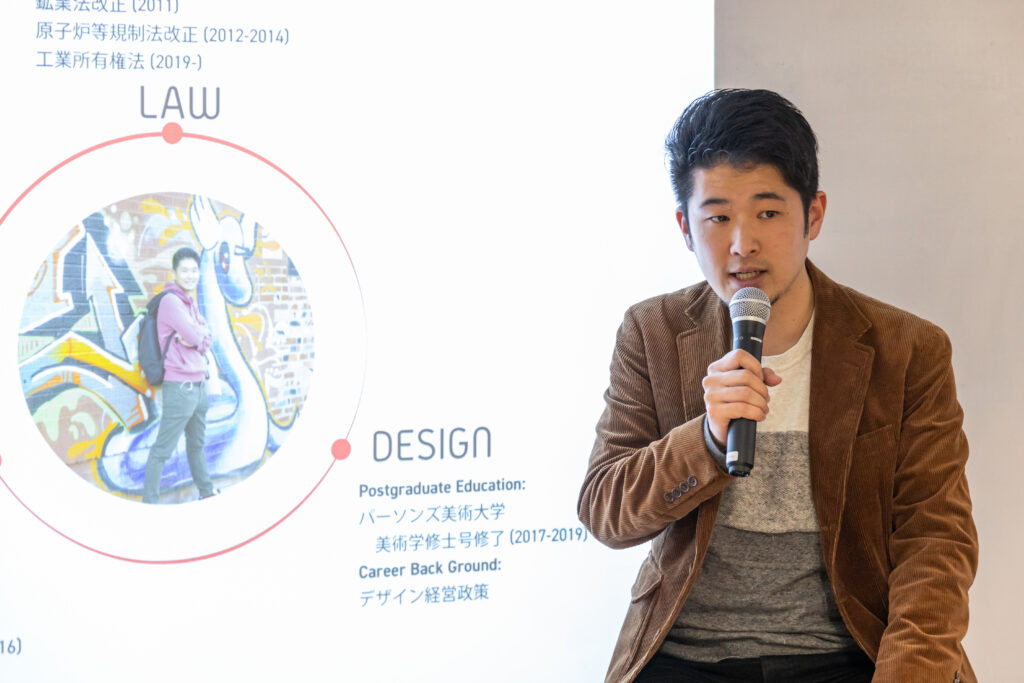
たとえば、課題設定については、内閣や産業界など、周囲や外部の意見を集めるより前に、行政官が自身の問題意識について考えることが大切だという。また、役所では組織の内外の声をすり抜けるように物事を進めがちだが、「イノベーションに衝突は不可欠。意見の衝突を避けようとするコンサバティブな組織像を変えることが必要だ」と話した。
一方、具体化では、トップと現場をつなぐ「ミドル・マネージャー」の重要性を指摘。政府からのトップダウンではなく、政府の大きなヴィジョンと、産業界などを含む現場の声の双方に耳を開く中間的な領域に、イノベーションの可能性があると語った。
「従来の政策立案プロセスは、調査をして課題を見つけ、社内検討をし、交渉や調整をするものでした。今後はむしろ、行政官がまず自分のヴィジョンを捉え、それを元に調査を行い、省内に限らない多様な立場の人と意見をぶつけながら政策の姿を探るプロセスが求められる。またそこでは、完全な政策実施に先立って、プロトタイプを通した検証を行うことも重要でしょう」
こうした新しい土壌からは、中小企業などに商標制度の理解を広めるため、カンフー映画を模したポップな動画を制作した「商標拳」という取り組みも生まれた。その動画は公開2週間で124万回再生、ウェブページの閲覧数も10万ビューの成果を上げた。

現在橋本さんは、2025年の大阪・関西万博に向け、知的財産のヴィジョン策定に携わっている。不安定で不明瞭な「VUCAの時代」と言われる現代。そのなかで今後のヴィジョンには、常識を前提にせず、「起こってもおかしくない」という視点が重要だと話す。
「たとえば、従来イノベーションの主体は企業でしたが、今後は情熱を持った個人が主体になる可能性もあります。では、個人が武器として特許制度や知財を使うためには、どんな制度が必要なのか。そんな『あり得る可能性』にも向けながら、現在、フリーランスのクリエイターの方などとも関わりつつ、その方向性を模索しています」
公共政策と人間中心デザインの重なるところ
続いて登壇した経産省デザイン政策室の菊地拓哉さんは、「政策のデザイン」の基本的な考え方をめぐる発表を行った。
2018年、「デザイン経営」宣言を発表した経産省では、より抽象的な分野も含むようになった近年のデザイン領域の広がりに対応して、地域デザイナーらのデザインプロデュース力を研修を通じて向上する「ふるさとデザインアカデミー」など、さまざまな取り組みを展開してきた。

ただ、この日のテーマの「政策のデザイン」は、イコール「デザイン政策」ではない。それはあらゆる政策に関わるものであり、「デザイン政策のデザイン」もその一部だと菊池さんは指摘する。
そもそもデザインとは何か。「厄介な問題」の提唱者のリチャード・ブキャナンや、工学者の吉川弘之の考えを引きながら、菊池さんはそれを「人を中心に据えた価値創造・問題解決の営み」と捉える。一方で公共政策とは、「公共的問題を解決するための解決の方向性と具体的手段」だ。両者は意外にも近く、公共政策のなかにデザインの考え方が内在しているとも言える。
「人間中心のデザインの考え方と、公共政策の公共性の重なる場所。そこに政策のデザインの領域はあると思います。その方向性は、役所中心ではなく人間中心、理性ではなく感情、縦割りではなく領域横断的などと言うことができるでしょう。一方、近年では、EBPM(エビデンスに基づく政策立案)といって、データ重視の企画立案プロセスも注目されています。こうした多様なアプローチがあるなかで、デザインに何ができるかを考えることが重要だと思います」

行政とデザインをめぐる先駆的な事例としては、国外では、省庁横断のデザイン組織であるデンマークの「MindLab」や、自治体などに向けウェブサイトの雛形を提供したイギリスの「Government Digital Service 」などが挙げられる。
国内では、2017年の「デジタル・ガバメント推進方針」 が、利用者中心の行政サービス改革を推進すると打ち出したことが大きかった。また、経産省が昨年発表したレポート「21世紀の『公共』の設計図」 では、デジタル時代の公共のあり方が模索された。さらに、県民の本音を行政経営の起点にすると謳った滋賀県の「Policy Lab. Shiga」など、地方自治体の試みも増えている。
「おそらく多くの政策立案者は、ここで語ったようなプロセスを魅力的に感じるはず。しかし現状では、評価の難しさや手間の多さがその歩みの障害になっています。そのなかで、今後やるべきなのは、各省庁に点々といる実践者たちをつなぐことや、成果の発信とナレッジの共有、さらに政策デザインに関する調査・研究を充実させることではないかと思っています」
リアルな人間に寄り添う、「ナッヂ」の活用を
クリエイティブイノベーション学科教授の長谷川敦士は、具体的に政策のデザインを進めるさいのポイントとなる視点について発表を行った。キーワードは「ナッヂ nudge」だ。
「ナッヂ」とは「つつく」の意味で、行動経済学では、人から非意識的な行動を引き出すための仕組みのことを指す。たとえば、オランダの空港で男性用便器の内側にハエの絵を描いたところ、清掃が楽になったという事例がある。人間の「的を狙いたくなる性質」をつつくことで、利用者は無意識のうちにトイレの衛生維持に貢献したわけだ。

こうしたナッヂの活用は、現在、行政から民間にまで広がっている。
2018年、イギリスで生まれたBehavioural Insights Team (BIT、通称ナッジ・ユニット)という政府組織では、消費から犯罪対策、教育などまで、幅広い公共サービスの改善にナッヂの知見を活用している。たとえば、「車両税の非納税者への手紙に車の写真を添付し支払率を上げる」「宝くじを利用して選挙の参加率を上げる」などはその具体例だ。BITは現在では民営化し、ロンドンやニューヨーク、シンガポールなどに拠点を広げている。
また、2015年にアメリカで設立された保険会社「レモネード」では、行動経済学者をチームに迎えている。通常、事故や病気などがなかった場合、保険料はそのまま保険会社のものになるが、同社では、加入時に支援したいチャリティ団体を選択し、未請求分の保険料をその団体への寄付に回す仕組みを設けることで、加入者の損失感をカバーし、納得感を高めている。

「行動経済学では、人は多くの判断を『思考』によってではなく『感情』に基づいて行っていると説明します。誰もが十全な注意や時間、完全な情報をもとに冷静な判断をするわけではない。むしろ、忙しさや不完全な情報のなかで感覚的な判断を行うことこそ、リアルな人の姿。そのリアリティにこそ、目を向ける必要があります」と長谷川。
さらに、臓器提供の意思表示に関する設問の例も挙げられた。「臓器提供を望むか?」「臓器提供を拒むか?」。こうした設問の違いによって、各国の提供率には実際に大きな開きが出ているという。日本は前者のような問いを採用しているが、こうした国の提供率は、後者を採用する国に比べて著しく低い。大きな社会的イシューが、設問のデザインによって左右されているのだ。

アメリカの作家、キム・グッドウィンによる「Bring Back “Human-Centered ”(人間中心を取り戻せ)」という主張のように、行政から民間まで、あらゆる事業にまつわる意思決定をリアルな人の姿を前提にした人間中心の視点で行っていくことが大事だ、と長谷川は語る。
「今日述べたナッヂの考え方は、政策デザインにも有効であると同時に、下手をすれば国民を一方向に導く危険性もあります。政策デザインの議論をするさいは、市民に誠実な意思決定を果たすための透明性やオープン性が重要ではないでしょうか。そこで得た信頼をもとに、市民が主体的に議論に参加できる場を構築していくこと。それがポイントかなと思います」
法律に見る、政策を「みんなのもの」とする視点
最後に登場したクリエイティブイノベーション学科教授の山﨑和彦は、今回のイベントの背景にある問題意識や、同学科大学院で実際に行われているプロジェクトなどについて紹介した。
今回の主催であるソーシャルクリエイティブ研究所は、「日本をデザインする」「みんなのためのデザイン教育」「これからの生活のデザイン」の三つのヴィジョンを掲げ、多様な立場の人々からなる「ソーシャルクリエイティブイニシアチブ」というコミュニティも運営している。
今春には、公共政策をデザイン視点で考える「政策のデザインラボ」も設置した。この日の催しはそのプレイベントでもある。このラボでは、大学で研究されているソーシャルデザインやサービスデザイン、あるいはプロトタイピングの知見などを、公共政策に生かすことが目指されている。
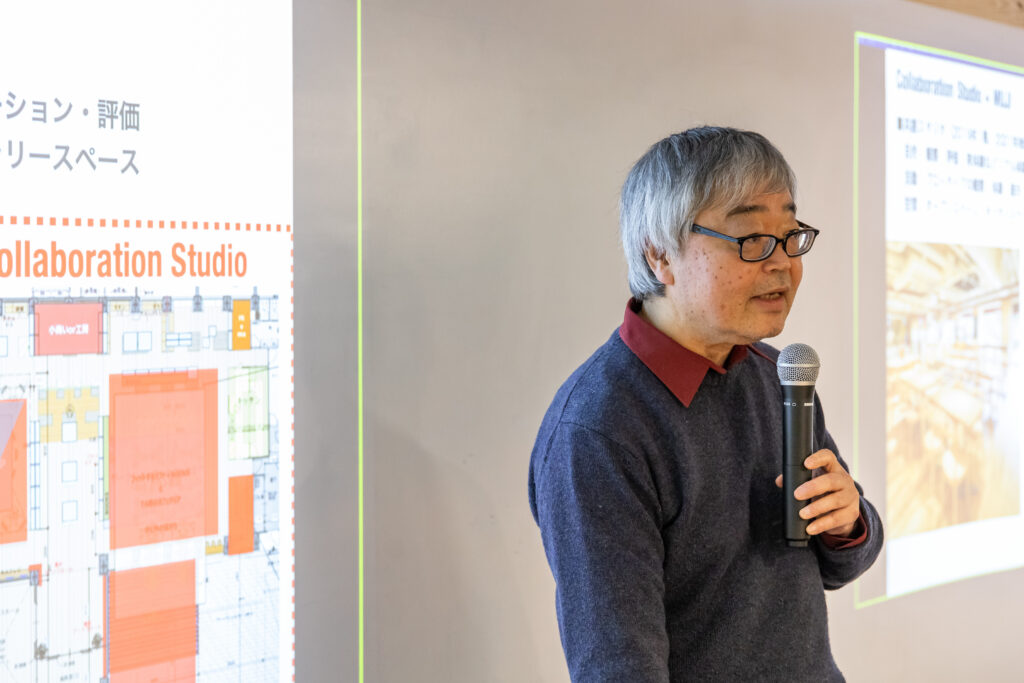
こうした背景のもと、昨年、クリエイティブイノベーション学科の大学院では、「未来のデザイン政策のヴィジョン」と「未来の法律とデザインのヴィジョン」という演習を行なってきた。その具体的な取り組みのひとつが、「みんなのための法律プロジェクト 」である。これは、一般的に馴染みが薄い法律の存在を、デザイン視点で捉え直すことを目的にした取り組みだ。
多くの市民にとって、法律とは、単に「守る」べき対象と捉えられがちだろう。だが、そこに「改善する」「作る」「活用する」といった視点を加えることができれば、法律は市民や企業にとってもっと身近で、武器にできるものになるのではないか、と山崎は言う。
たとえば、これまで法律の積極的な活用者は、弁護士など一部の専門家に限られていた。だが近年では、テクノロジーを通じて相談者と専門家の間をつなぐ「法テラス」や「弁護士ドットコム」のような試みも生まれてきている。また、そもそも法を「守る」ことが重要なのは、市民自らが立法のプロセスに参加しているからだが、ニューヨークの「The New York State Senate」というサイトでは、州の立法プロセスを親しみやすいグラフィックなどを用いて「見える化」している。

一方、法律は時代に合わせて「改善」されるものだ。インターネット時代の新しい著作権のあり方を民間から提案した「クリエイティブ・コモンズ・ライセンス」や、誰もがある議題についてのオンライン署名を募れる「Change.org」などは、その具体的な提案やツールの例である。こうした土壌において、今後は市民が行政と一緒に法律を「作る」ことが大切になる。カナダのトロントから生まれたデジタルプラットフォーム「citizenlab」は、市民が政策のアイデアを投稿し、それをみんなで議論するとともに、投票やアンケートを通して磨いていく場として活用されている。
「重要なのは、この『法律』という対象を、『政策』に置き換えることもできることだ」と山崎。普段は意識されない「政策」のブラッシュアップについても、こうした「改善する」「作る」「活用する」「守る」という観点の整理によって、より具体的に進めることができると指摘した。
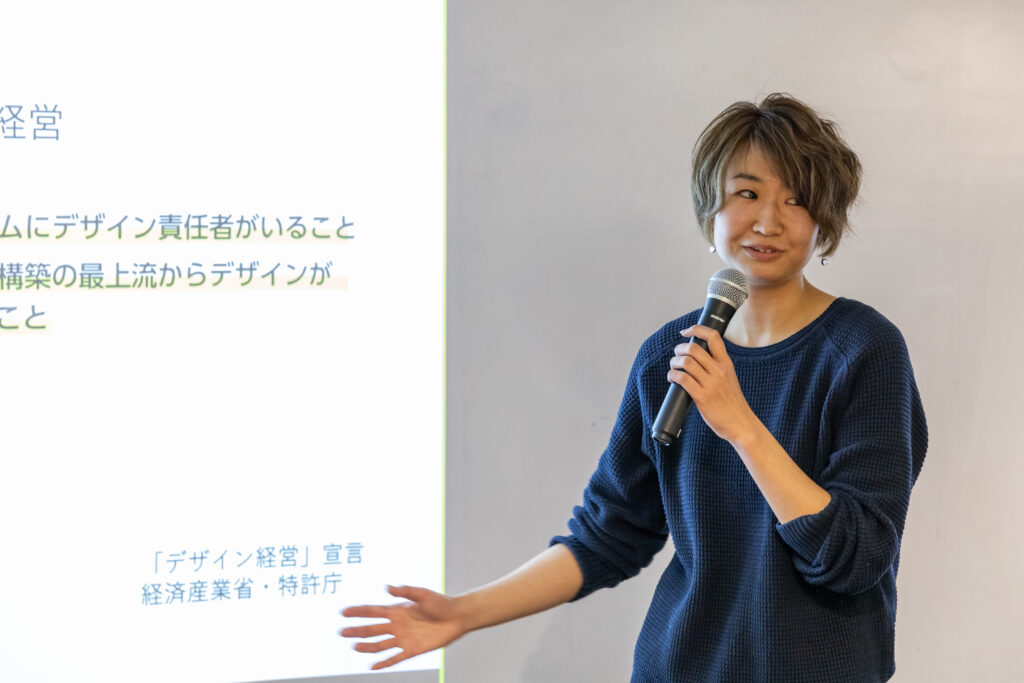
また、山崎の発表に続いては、大学院生たちがこの一年間で考えたサービスや政策のアイデアに関する発表も行われた。たとえば、災害発生に先立って個人の特性を事前登録できるボランティア情報制度や、年齢に縛られない個人の活躍の拡大を目指すポートフォリオ制作の仕組みなど、多様なアイデアが語られた。大学院生の発表に、スピーカーたちも熱心に聞き入っていた。
多様な市民を巻き込む、「パブリック」意識の重要性
イベントの後半では、「政策のデザインラボ」の研究員である博報堂の岩嵜博論さん、専修大学の上平崇仁さん、特許庁の外山雅暁さんも加わり、ディスカッションが行われた。
話題のひとつとなったのは、「政策のデザイン」の領域について。勤務先でもこのテーマを研究している上平さんは、この問題を語るさい、「立案プロセスのデザイン」と「個別政策のデザイン」の二つが混同されがちだと指摘。そのうえで、従来の政策は、行政機関で作られ、一般の市民のもとに「降りてくる」イメージが強かったが、実際は両者のあいだにより大きな「パブリック」の領域があるとし、市民が「自分ごと」としてその領域に関わることの重要さを話した。
「政策のデザイン」の領域の内訳を整理する重要性は、菊池さんからも聞かれた。一方で橋本さんは、「立案プロセス」と「個別政策」のデザインには地続きの部分もあるとして、何より大切なのは、上平さんも言うように、多様な人がそのプロセスに参加することだと語った。

そうした「パブリック」への多様な人々による参加は、どのように可能なのか。上平さんは、北欧では図書館ひとつとっても、そこを「みんなの場所」としてデザインし、結果としてその施設が市民の誇りとなって人々のデザイン意識を高めるような、良いサイクルがあると話す。
しかし、日本では「市民参加型デザイン」がなかなか根付いていないのも事実だ。山崎は、そこで必要なのは、日本のデザイン文化や企業文化の根本的な改革だと指摘した。これに対して、外山さんは、「デザイン経営」宣言にはまさに企業のデザイン意識を変える狙いがあると語った。
さらに外山さんは、「デザイン経営」について中小企業の経営者に聞き取りを行うなかで、経営者の危機感の有無が変化の大きなポイントだと感じた、と言う。長谷川はこの話を受け、一般的には別物と考えられる「ヴィジョン」と「危機感」は、知識や経験の蓄積の上に図らずも「見えてしまうもの」であるという点において、構造的に似ていると語った。
一方で、参加型デザインについては、都市計画や建築分野ですでにそれなりの蓄積があるという岩嵜さんの指摘もあった。たとえば、公園のような公共空間の計画では、設計と並行して市民向けのワークショップなどを開くことも多い。こうした先行例のスタディも、今後の課題だろう。

最後に山崎からは、あらためて研究の重要性が語られた。「日本の行政や企業には、研究や実験をせずにアイデアだけを求める傾向がある。けれど、北欧をはじめとする先駆的な国には、研究を通して新しいアイデアを見つけようという姿勢がある」と山崎。「このラボは、行政との関わりのなかでそんな機能を果たしていくことができるはず」と話し、イベントをまとめた。
text 杉原環樹(ライター)
photo 星野耕史
